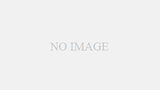年々、需要が高まってきている「相続土地国庫帰属制度」ですが、申請が承認された際に納付するが負担金が必要となります。今回は、申請する際に非常に気になる「負担金」に絞って解説していきます。
負担金の概要
相続土地国庫帰属制度の負担金は、土地の性質を考慮した管理費用で、10年分の土地管理費用相当額を基準に算定されます。
負担金(土地)の分類
負担金を算定するために、申請された土地を4種類に区分し、種目に応じて負担金額が算定されます。
種目は、「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分されます。
負担金の算定方法
原則として、負担金は20万円となっておりますが、土地の分類によって異なり、面積に応じて算定する場合もございますので、注意が必要です。
4種類に区分された負担金の算定方法は以下の通りです。
| ①宅地 | 原則、20万円 ※但し、都市計画法の市街化区域、または用途区域が指定されている場合は、面積に応じて算定 |
| ②農地 | 原則、20万円 但し、以下の農地については面積に応じて算定 ①都市計画法の市街化区域、または用途区域が指定されている場合 ②農地振興地域の整備に関する法律の農用地区域の場合 ③土地改良事業等の施行区域の場合 |
| ③森林 | 面積に応じて算定 |
| ④その他 ※原野、雑種地など | 原則、20万円 |
上記、①宅地②農地③森林の種目に該当し、かつ「面積に応じて算定」が必要な場合は、以下の表を基に算定します。
| ①宅地の場合 | |
| 50㎡以下 | 面積に4,070(円/㎡)を乗じ、208,000円を加えた額 |
| 50㎡超100㎡以下 | 面積に2,720(円/㎡)を乗じ、276,000円を加えた額 |
| 100㎡超200㎡以下 | 面積に2,450(円/㎡)を乗じ、303,000円を加えた額 |
| 200㎡超400㎡以下 | 面積に2,250(円/㎡)を乗じ、343,000円を加えた額 |
| 400㎡超800㎡以下 | 面積に2,110(円/㎡)を乗じ、399,000円を加えた額 |
| 800㎡超 | 面積に2,010(円/㎡)を乗じ、479,000円を加えた額 |
| ②農地の場合 | |
| 250㎡以下 | 面積に1,210(円/㎡)を乗じ、208,000円を加えた額 |
| 250㎡超500㎡以下 | 面積に850(円/㎡)を乗じ、298,000円を加えた額 |
| 500㎡超1,000㎡以下 | 面積に8100(円/㎡)を乗じ、318,000円を加えた額 |
| 1,000㎡超2,000㎡以下 | 面積に740(円/㎡)を乗じ、388,000円を加えた額 |
| 2,000㎡超4,000㎡以下 | 面積に650(円/㎡)を乗じ、568,000円を加えた額 |
| 4,000㎡超 | 面積に640(円/㎡)を乗じ、608,000円を加えた額 |
| ③森林の場合 | |
| 750㎡以下 | 面積に59(円/㎡)を乗じ、210,000円を加えた額 |
| 750㎡超1,500㎡以下 | 面積に24(円/㎡)を乗じ、237,000円を加えた額 |
| 1,500㎡超3,000㎡以下 | 面積に17(円/㎡)を乗じ、248,000円を加えた額 |
| 3,00㎡超6,000㎡以下 | 面積に12(円/㎡)を乗じ、263,000円を加えた額 |
| 6,000㎡超12,000㎡以下 | 面積に8(円/㎡)を乗じ、287,000円を加えた額 |
| 12,000㎡超 | 面積に6(円/㎡)を乗じ、311,000円を加えた額 |
例:80㎡の宅地の場合(市街化区域)
80㎡×\2,720+\276,000=\493,600 となります。
※面積に応じて算定が必要な場合、高額になる傾向にあります。
合算負担金について(軽減措置)
隣接する2筆以上の土地で、区分(及び条件も)が同一の場合は、複数の土地を1つとみなして「合算負担金の申し出」を行うことができます。
※土地の所有者が異なる場合でも共同して申請することができます。
例:隣接する宅地(市街化区域)の土地A(30㎡)と土地B(150㎡)を計算した場合
<通常計算の場合>
30㎡×\4,070+\208,000=\330,100(土地A)
150㎡×\2,450+\303,000=\670,500(土地B)
(土地A)+(土地B)=\1,000,600
<合算の場合>
(30㎡+150㎡)×\2,450+303,000=\744,000
※合算負担金の申し出を行った場合、\256,600もお得になります。
まとめ(注意事項)
負担金の算定方法について詳しく解説しましたが、次のステップとして法務局への相談や申請になると思われます。
事前相談は予約制となっており、その土地の都道府県の本局が相談先&申請先となっていることに注意が必要です。(支局や出張所では受け付けていません。あくまでも本局のみです。)
※宮城県で言えば、仙台法務局(仙台市)のみで受け付けております。