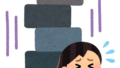土地、建物の登記を生業としておりますと、切っても切れない関係に「相続」があります。
土地家屋調査士が不動産の相続登記を行うことはありませんが(司法書士が行います)、相続が発生していることで、時間が予想以上に掛かる場合があります。
問題になる相続について(一例)
依頼者が相続の権利を有していない
【事例】:祖父(亡くなっている)が所有者として登記されている建物が、既に現地になく取り壊されて無くなっているため、建物滅失登記を依頼されたので戸籍を調査したところ、依頼者が法定相続人ではなかった。
【結果】⇒建物所有者が既に亡くなっている場合、建物所有者の法定相続人の1人から建物滅失登記が可能だが、戸籍を調べた結果、依頼人の父(次男)の兄弟(長男)が「家督相続」しており、依頼者(孫)が相続権を有していなかった。(家督相続した方の息子様にお願いし、建物滅失登記を行った。)
※家督相続とは…明治31年~昭和22年まで施行されていた旧民法の相続制度で、一般的に長男がすべての財産を引き継ぐことになります。
遺産分割協議書に「未登記建物」の相続について記載がない
「事例」:現地の建物が、登記の内容と合致しないため(母屋が増築されており、離れの建物があった)、「建物表題部変更登記」の依頼があった。過去に遺産分割協議書により相続登記されたものだったため、改めて確認したところ、遺産分割協議書には登記建物のみが記載されており、増築された部分や離れの建物についての記載がなかった。
【結果】⇒課税(固定資産)の対象にもなっていないことから、隣接者の証言書(実印、印鑑証明)及び上申書(申請人)を取得し、これを所有権証明として「建物表題部変更登記」を行った。
証言書の作成はハードルが高く、時間と費用を要します。
遺産分割協議書に以下の一文追加することにより、未登記の建物も相続対象とすることができます。
例1:「〇〇の土地上の建物は、すべて△△△が相続する」
例2:「財産目録にないものは、すべて◇◇◇が相続する」
※相続の状況により、上記のような記載が難しいものもございますが、、、
相続人のひとりであることを認識していない(又は誤認している)
【事例】:土地の隣接所有者が既に亡くなっているため、戸籍等を調査し、相続人に立会い依頼を行ったところ、「相続人でない」との理由で拒否された。
【結果】⇒特別な事情があったかもしれないが、戸籍等において法定相続人であることは明らかであるのにも関わらず、「自分が正しい」との認識で、取り合ってもらえなかった。
※説得(説明)出来なかった、自分自身の力不足が原因です。
相続放棄と遺産放棄を勘違いしている
【事例」:土地の隣接所有者が既に亡くなっているため、戸籍等を調査し、相続人に立会い依頼を行ったところ、「相続放棄している」との理由で拒否された。(事例2と似ているが…)
【結果】⇒「相続放棄」は、法的な手続きによって効力を発揮するもので、家庭裁判所への申し立てを行う必要があること(被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に行う必要がある)から、遺産を受け取らないことの意思表明をするだけの「遺産放棄」であることが分かった。
遺産分割協議を行った経緯も無いことから、「相続権を有している=管理義務が生じる」旨を説明し、立会い&同意を得た。
「相続放棄している」という言葉だけでは、法的根拠はなく、相続をしない(したくない)との意思表明だけでは「相続」から逃れることはできません。
例え、相続人全員が「相続放棄」しても「相続財産管理人」が選任されるまで、相続人には財産の管理義務が生じます。
※また、「相続財産管理人」の選任は、「相続放棄」と同様に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
まとめ
相続については、戸籍等の資料調査や聞き取りなどから事情が明らかになることも少なくありません。
不明なことは、できる限り分かりやすく説明いたしますので、ご協力をお願いいたします。